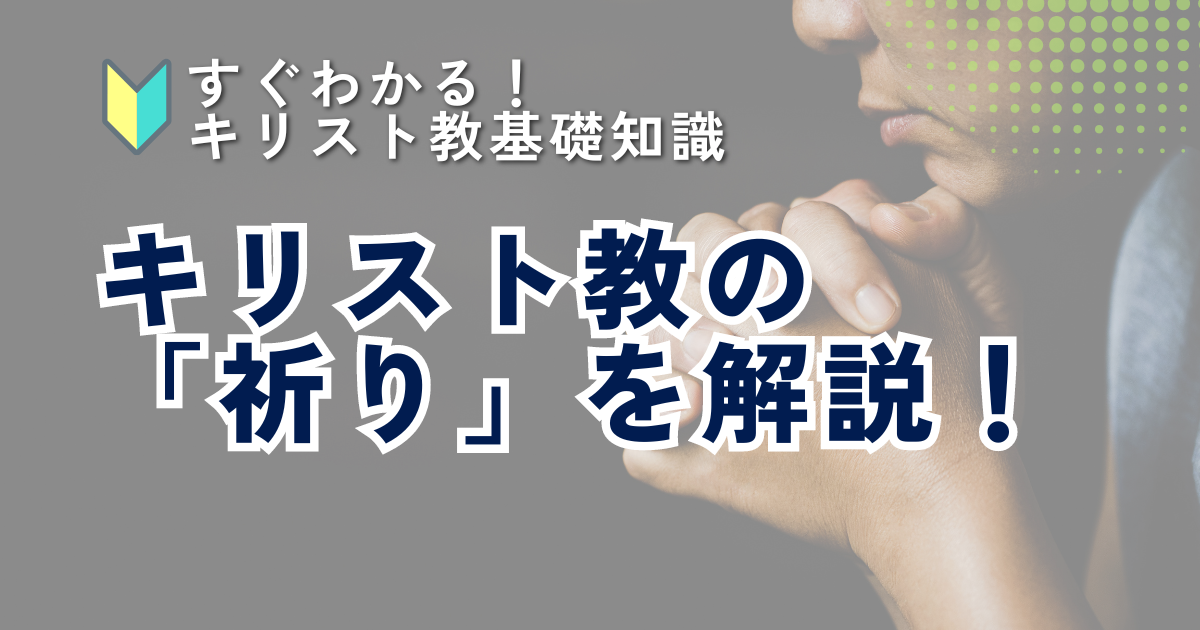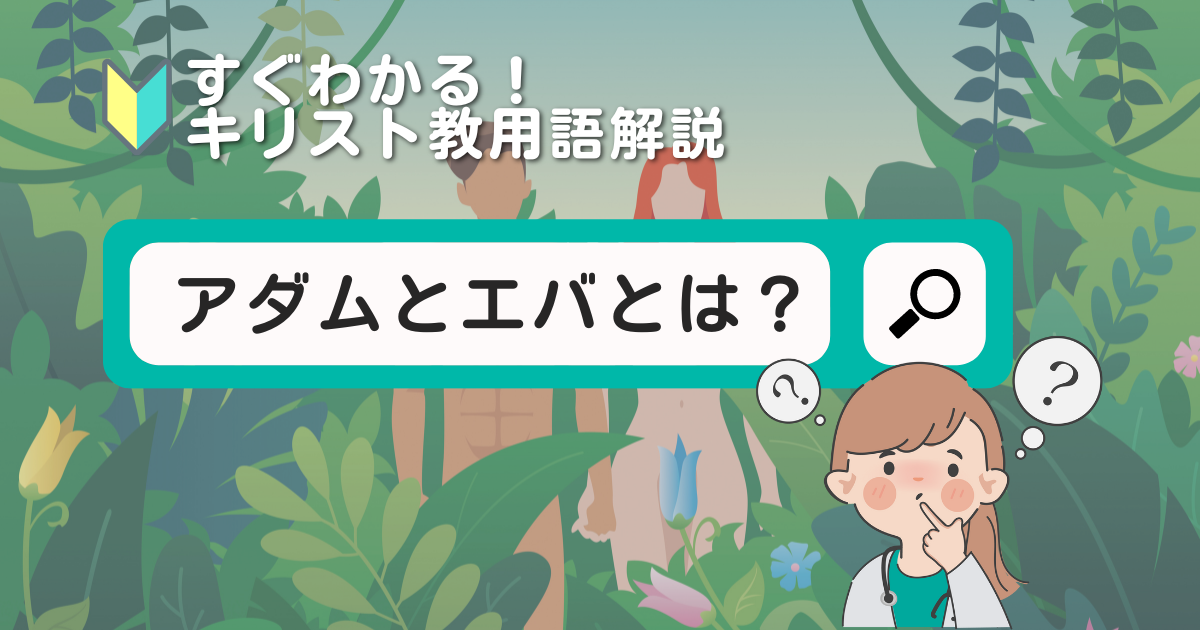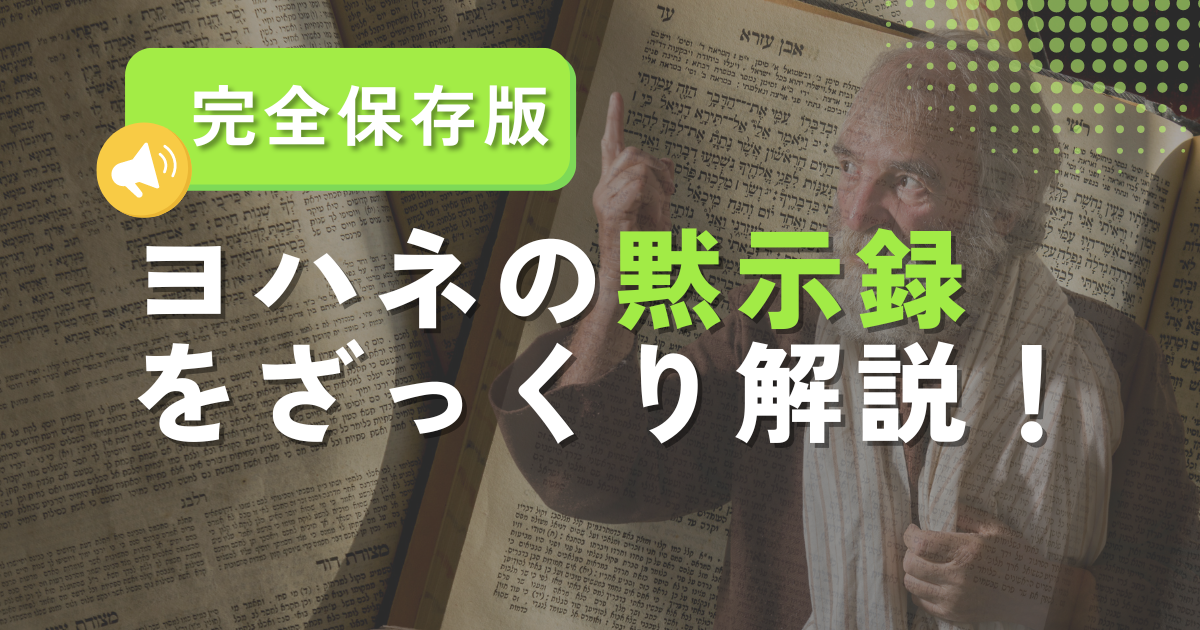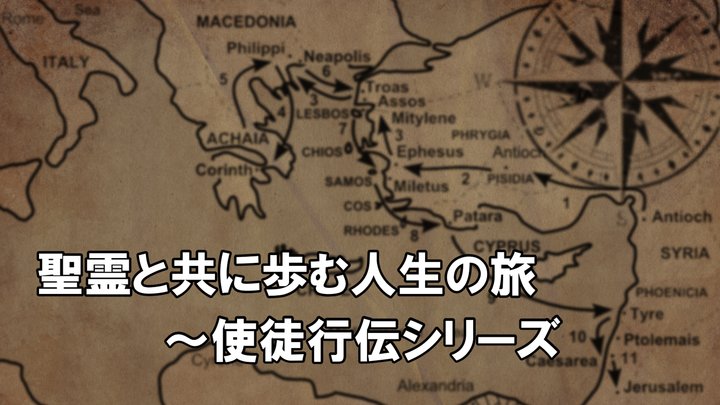この記事は約9分で読むことができます。
キリストの復活はいつから伝えられたのか?
キリスト教で言われる「キリストの復活」は本当にあったのでしょうか?
コリントの信徒への手紙一15章から、このことについて考えてみましょう。
15:13もし死人の復活がないならば、キリストもよみがえらなかったであろう。15:14もしキリストがよみがえらなかったとしたら、わたしたちの宣教はむなしく、あなたがたの信仰もまたむなしい。(中略)15:16もし死人がよみがえらないなら、キリストもよみがえらなかったであろう。 15:17もしキリストがよみがえらなかったとすれば、あなたがたの信仰は空虚なものとなり、あなたがたは、いまなお罪の中にいることになろう。1コリント15:14-17(口語訳)
コリントの信徒への手紙一15章で、パウロは2回も繰り返し、キリストの復活が信仰の中心であることを述べています。パウロは復活の事実を短く次のようにまとめています。
15:3わたしが最も大事なこととしてあなたがたに伝えたのは、わたし自身も受けたことであった。すなわちキリストが、聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のために死んだこと、 15:4そして葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、三日目によみがえったこと、 15:5ケパに現れ、次に、十二人に現れたことである。 15:6そののち、五百人以上の兄弟たちに、同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちもいるが、大多数はいまなお生存している。1コリント15:3-6(口語訳)
ここでは「最も大事なこと」がキリストの十字架と復活であると、はっきりと述べられています。コリントの信徒への手紙一は、使徒パウロが第3次伝道旅行で3年間(AD54―57年)活動したエペソから書かれました(1コリント16:8)[1]。
キリストのバプテスマと公生涯の開始がAD27年の秋ごろであり(ルカ3:1)[2]、それから3年半経ったAD31年の春に十字架にかけられたとすると、わずか約25年後に復活の記録が文書にまとめられたのです[3]。
さらに「以前あなたがたに伝えた福音」という表現からもわかるように、この手紙が書かれるよりも前から、この「教え」は存在していました。多くの学者によって、十字架後の3年から8年にはすでに使われていたと主張されています[4] 。
第一に、おそらく最も重要なことは、新約聖書の初期の書物は、史的イエスの生涯、特にイエスの死と復活に十分な関心を示しているということです。(中略)コリントの信徒への手紙一15章3節に、このような関心を示す最も重要な証拠が含まれているのは偶然ではありません。パウロは、この著書よりもずっと古い、非常に初期のキリスト教信条を取り入れているのです。このような初期の伝承は、新約聖書に頻繁に登場し、書物に記録されるまでに繰り返された口伝の教えや宣言から成っています。つまり、これらの信条は、新約聖書に登場するよりも古いものなのです。この伝承はイエスの死、埋葬、復活、出現を報告し、死後三日目に復活したことを語っています[5]。

死んだキリスト
さて、このころイエスという賢者がいた。彼は素晴らしい行為を成す人で、喜んで真理を受け入れる人々の教師であった。彼は多くのユダヤ人と異邦人を引き寄せた。我々の指導者たちの示唆に基づいてピラトが十字架刑を彼に宣告したとき、彼をはじめから愛していた人たちは彼を捨てなかった。そして彼の名をもって名付けられたキリスト教徒は、今日も現存している[6]。
フラウィウス・ヨセフスという古代のユダヤ史家が残したこの言葉は、フラウィウス証言として知られています。
証言の中にはキリストのことをほのめかす言葉が追加されたかもしれないという証拠がありますが、ヨセフスのものであることが明白な部分のみを見ても、キリストが実在し、十字架にかかったという事実は明らかです[7]。

十字架刑の死因は窒息死で、足首を折ると呼吸がさらに難しくなるために、対象者の死を早めることになります。
ローマ兵はこのようなことに精通していたようで、最近発見されている1世紀に行われた十字架刑の犠牲者たちを見ると、足の骨は折れています[8]。キリストの十字架の時も同様の方法で、対象者を確実に処刑していました(ヨハネ19:32,33)。
またヨハネはキリストがやりで突かれたことと、「血と水が流れ出た」ことを記しており、(ヨハネ19:34)この描写によってやりが確実にキリストの心臓を貫いたことを明らかにしています[9]。
やりは右肺から心臓に達し、引き抜くときに水のように見える心嚢水と胸水、そして大量の血液が体外に出たのです。
極度のストレスにさらされ、血汗症を発症していたキリストは(ルカ22:44)、鞭打ちの刑を受けられました(ヨハネ19:1)。
ローマ帝国の鞭打ち刑は肉を削ぎ落とすようなもので、その影響で血液量が減少し、十字架にかけられたときには、すでにキリストはショック状態になっていたと考えられています(ヨハネ19:28)[10]。
空の墓
どのような学者たちであっても、以下の流れが歴史的にあったことを認めています。
- キリストは十字架で死んだ
- 墓に葬られた
- キリストの死によって、弟子たちは絶望した
- 数日後に墓が空であることが発見された
- 弟子たちが復活したキリストが現れたと信じる経験をした
- 弟子たちがキリストの死と復活を大胆に述べ伝えるものへと変貌した
- 懐疑的だったヤコブや敵対勢力にいたパウロも信じていった。
ドイツの歴史家ハンス・フォン・カンペンハウゼンはコリントの信徒への手紙一15章3節について、次のように述べています。
この記述はこのようなテキストに対してなされ得る歴史的信頼性の要求をすべて満たしている[11]。
つまり十字架から25年後に、キリストが復活したことを敵対勢力にいたことがある人物によって、歴史的な信頼性を持って宣言されたのです。もっと言うなれば、信条としては十字架から3年後に成立していた可能性もありました。
この箇所が信条として成立していたという証拠には、コリントの信徒への手紙一15章1節にラビの専門用語で宗教的な伝統の継承のときに使われる表現が出てくることなどが挙げられています[12]。
この聖句で、少なくともキリストの死と埋葬、そして弟子たちが復活したキリストが現れたと信じる経験をしたことが明らかであることがわかります。
28:11女たちが行っている間に、番人のうちのある人々が都に帰って、いっさいの出来事を祭司長たちに話した。 28:12祭司長たちは長老たちと集まって協議をこらし、兵卒たちにたくさんの金を与えて言った、 28:13「『弟子たちが夜中にきて、われわれの寝ている間に彼を盗んだ』と言え。 28:14万一このことが総督の耳にはいっても、われわれが総督に説いて、あなたがたに迷惑が掛からないようにしよう」。 28:15そこで、彼らは金を受け取って、教えられたとおりにした。そしてこの話は、今日に至るまでユダヤ人の間にひろまっている。マタイ28:11-15(口語訳)
マタイによる福音書28章を見ると、敵対勢力の祭司長たちが「弟子たちが盗んだ」ことにして、空となったキリストの墓の説明をしようとしていることが描かれています。
この論争は、後のユダヤ教のラビによって書かれた書物にも記録されていますが、「墓が空になっている」ことを前提としているのです[13]。
この問題に関するユダヤ最古の論争は、空の墓が史実であることを前提に進められています。墓の中にイエスの遺体があるかどうかについて議論している人は誰もいません。問題はいつも「遺体はどうなったのか」というポイントなのです[14]。
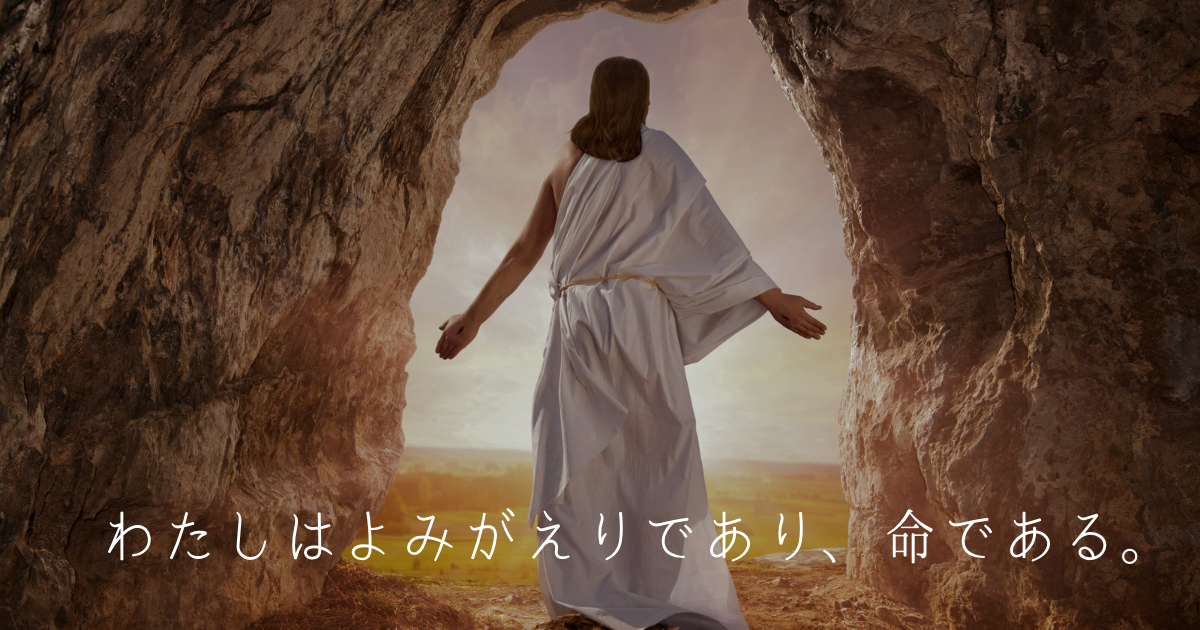
使徒現行録2章24節では、ペテロがエルサレムではっきりとキリストの復活を宣言している場面が出てきます(使徒2:24)。
敵対勢力はキリストの墓の場所を知っていたので、もし墓の中に遺体があれば、このときに反論することは容易いことでしたが、できませんでした。
その結果、使徒言行録2:41によると「そこで、彼の勧めの言葉を受けいれた者たちは、バプテスマを受けたが、その日、仲間に加わったものが三千人ほどあった」のでした(使徒2:41)。
それは、人々がキリストの墓を見に行くことができ、そして、キリストの墓が空になっているのを目にすることができたからではないでしょうか。
では、当時の指導者たちが言ったように弟子たちが盗むことは可能なのでしょうか。マタイによる福音書27章を見ると、当時の指導者たちは弟子たちが盗もうとするのではないかと恐れていたのがわかります。
「長官、あの偽り者がまだ生きていたとき、『三日の後に自分はよみがえる』と言ったのを、思い出しました。 ですから、三日目まで墓の番をするように、さしずをして下さい。そうしないと、弟子たちがきて彼を盗み出し、『イエスは死人の中から、よみがえった』と、民衆に言いふらすかも知れません。そうなると、みんなが前よりも、もっとひどくだまされることになりましょう」。 ピラトは彼らに言った、「番人がいるから、行ってできる限り、番をさせるがよい」。 そこで、彼らは行って石に封印をし、番人を置いて墓の番をさせた。マタイ27:63-66(口語訳)
当時、警備の失敗は死にもつながることでした(使徒16:27)。加えて、弟子たちが10人以上いたことや民衆に歓迎されたエルサレムに入城したキリストの姿(マタイ21:9)を知っていることから、警備が10人以上の兵士によってなされたことは確実です。一説では100名近い兵士が派遣されていたとされています[15]。
このように、墓から遺体を盗むのは命懸けでした。また、同じような時代に発布された法令では、墓荒らしに対して死刑が執行されることが言及されています[16]。キリストを失ったと思い、失意の底にいた弟子たちが命をかけて遺体を盗むことができたとは思えません。
さらに、当時の社会の中で地位が低い女性が空になった墓を見つけた証言者として描かれているのも、とても興味深い事実です。女性の証言は意味がないと考えられており、法廷においてもその証言が認められることがないほどでした。その社会において、女性が証言者として登場している福音書の記述はその事実に信憑性を加えていきます[17]。
いずれにしても、もし弟子たちが遺体を盗んだのであれば、彼らのその後の人生の変化に対する説明がつきません。
もし弟子たちが遺体を盗んだのであれば、彼らは周知の嘘や詐欺のために死ぬことを望まなかったでしょう。
さらに、初期の弟子たちの生活の変化や、イエスがよみがえったという彼らの信念は、批評家たちが認めていることですが、彼らが死体を盗んだとすれば、説明がつかないのです。
この告発は、復活したイエスを見た二人の不信心な懐疑論者、パウロとイエスの兄弟ヤコブを考慮していません。彼らはそのような詐欺によって、確信することはなかったはずです。
このほか、弟子たちの倫理的な教えの質など、いくつかの点を考慮した結果、批判的な学者たちによってさえ、この見解が退けられることになったのです[18]。
復活の証言
キリストの死、空の墓、弟子たちの変貌。これらの事実から導き出されることは「キリストの復活」の可能性です。
懐疑的な歴史学者でさえ、原始キリスト教にとって、……イエスの死からの復活は、歴史上の現実の出来事であり、信仰のまさに基礎であって、信者の創造的な空想から生じた神話めいた考えではないことに同意しています[19]。
パウロにとって、キリストの復活が現実であったことは、コリントの信徒への手紙一15章で明らかになっています。
15:3キリストが、聖書に書いてあるとおり、わたしたちの罪のために死んだこと、 15:4そして葬られたこと、聖書に書いてあるとおり、三日目によみがえったこと、1コリント15:3-5(口語訳)
「死んだこと」と「葬られたこと」は原語を見てみると、過去形で書かれており、「よみがえったこと」だけは、今もなお継続している意味を示す完了形で書かれています。キリストはよみがえり、そして生き続けておられるのです。キリストはたしかに復活されました。
そして、その当時はまだ大多数が生存していた復活したキリストを目撃した500人以上の兄弟たちによって、この事実が裏付けられるとパウロは述べています(1コリント15:6)。
現代人の感情はイエスの復活のようなことは信じません。しかしながら、歴史的証拠があまりに確かなために、復活を信じない人々でさえ、多くの人が復活したイエスを見たと信じていることを認めざるを得ません[20]。
参考文献
[1]Nichol, F. D. (Ed.). (1980). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 6, p. 103). Review and Herald Publishing Association.
[2]Nichol, F. D. (Ed.). (1980). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 5, p. 714). Review and Herald Publishing Association.
[3]Nichol, F. D. (Ed.). (1980). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 6, p. 799). Review and Herald Publishing Association.
[4]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (p. 154). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[5]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (pp. 29–30). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[6]Antiquities XVⅢ, 33, in lbid., 125..
[7]ロン・E・M・クルーゼ『神学博士が伝えたい神の言葉』福音社、83頁
リー・ストロベル『ナザレのイエスは神の子か?』いのちのことば社、127-130頁
[8]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (pp. 73–74). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[9]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (pp. 74–75). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[10]リー・ストロベル『ナザレのイエスは神の子か?』いのちのことば社、319-321頁
[11]Hans von Campenhausen, “The Events of Easter and the Empty Tomb,” in Tradition and Life in the Church (Philadelphia: Fortress, 1968), p. 44, as quoted by Ladd, I Believe, p. 105.
[12]リー・ストロベル『ナザレのイエスは神の子か?』いのちのことば社、376-378頁
[13]Simpson, W. J. S. (1909). Our Lord’s Resurrection. (W. C. E. Newbolt & D. Stone, Eds.) (Second Edition, pp. 97–98). London; New York; Bombay; Calcutta: Longmans, Green, and Co.
[14]リー・ストロベル『ナザレのイエスは神の子か?』いのちのことば社、364頁
[15]エレン・ホワイト『各時代の希望 下巻』福音社、308頁
[16]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (p. 176). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[17]リー・ストロベル『ナザレのイエスは神の子か?』いのちのことば社、358-359頁
[18]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (pp. 226–227). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[19]Habermas, G. R. (1996). The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ (p. 164). Joplin, MO: College Press Publishing Company.
[20]アルベルト・R・ティム『永遠の命』セブンスデー・アドベンチスト安息日学校部、56頁