
この記事は約5分で読むことができます。
「召し」の意味は?
「召し」とは?
「召し」とは、どのような進路を選ぶのか、どのようなキャリアアップをしていくのかという質問に答えるものではありません。
どのように神に献身していくのかという質問に答えるもので、また神の働きが明確化されるプロセスです。
そして、それは一時の感情や思いつきによって与えられるものではないのです。
宗教改革時に起こった「召し」の意味の移り変わり
中世キリスト教世界において、最高の召しとは司祭か修道士になることであり、そのような聖職に召されることを指すためだけに「召し」という語は用いられていた[1]。
ところが、この「召し」という言葉の意味は宗教改革を転機に意味が変わっていきます。
宗教改革時において、すべての労働はその価値において等しい、それゆえに私たちの労働のすべては神への奉仕であるべきだ、という風潮が高まった[2]。
ウィリアム・ティンダルは次のように教えました。
神を喜ばせるのに、ある労働が他の労働にまさるということはない。水を注ぐこと、皿を洗うこと、靴直しになること、使徒であることは、一つことである。皿を洗うことと福音を宣べ伝えることとは、神を喜ばせる行為において、全く一つである[3]。
カルヴァンもまた、「タラント」を霊的な賜物や恵みと理解してきた従来の解釈を排し、タラントを日常の労働や召しに関連づけていきます。
つまり、宗教改革の時から仕事とは神が派遣した場所であり、そこで神を証し、神と人とに奉仕すべき使命の場所であると理解され始め、「召し」と「労働」、「職業」が混ざり合い、宗教改革時に起こっていき、「召し」という言葉は、より広い意味を持つようになっていったのです。
職業を意味するドイツ語の単語はベルーフであるが、ここに宗教的な観念がこめられているのは明らかであり、これは英語のコーリングという語にはもっと明確に示されている。職業という語には、神から与えられた使命であるという観念が含まれるのである[4]。
ドイツ語のベルーフと同じような観念を保持しているのが、ヘブライ語です。מלאכהという単語が、祭司の職務について使われ、さらに王に奉仕する任務、労働監督の任務、農耕労働についての記述、手工業者についての記述に使用されています。
この語はלאכ(送る、派遣する)という語根から生まれたものであり、もともとは『使命』という意味を持っている[5]。
つまり、中世のカトリック社会の中において「召し」は「聖職」を意味していて、ヘブライ語の中では「使命」という意味を「職業」という言葉に見ることができるのです。
伝道者として召命を受けたかどうか
召されたものは伝える能力を持つ
神の「召し」について語るみことばの大多数は、救いに対する、また聖なる生活に対する召しに関するものである」[6]。
それゆえ、中世キリスト教世界において、「召し」を宗教的職業への献身と見なしたのは自然であるともいえるでしょう。
かつ、だれもこの栄誉ある務を自分で得るのではなく、アロンの場合のように、神の召しによって受けるのである。
ヘブル人への手紙5章4節(口語訳)
召命は神から来るものであり、自分の選択ではありません。そのため、多くの神のメッセンジャーが必ずしも最初から神の召しを快く受け入れたわけではありませんでした。
モーセは「わたしは口も重く、舌も重いのです」(出エジプト4:10)と言い、エレミヤも次のように言っています。「ああ、主なる神よ、わたしはただ若者にすぎず、どのように語って良いか知りません」(エレミヤ1:6)。イザヤでさえも、「わざわいなるかな、わたしは滅びるばかりだ。わたしは汚れたくちびるの者」(イザヤ6:5)と言いました。
注目したいのは3人とも召命を受けた際に、口や唇、語る言葉などに言及していることです。彼らは神からの召命とは、メッセージを伝えることであると知っていたのです。
神からの召命とは、「その人の意思とは関係なく、メッセージを伝えるように神に命じられること」ということができるのではないでしょうか。
一同が主に礼拝をささげ、断食をしていると、聖霊が「さあ、バルナバとサウロとを、わたしのために聖別して、彼らに授けておいた仕事に当たらせなさい」と告げた。
使徒行伝13章2節(口語訳)
ここでも信徒たちは自分たちの意志ではなく、神の意志に従うことが求められています。
召命にはメッセージを伝えることが欠かせないものであるとわかりましたが、召命された証拠としてメッセージを伝える能力があることを挙げることはできません。
人が上手に祈り、話すことができるという事実は、神がその人を召されたことの証拠ではありません[7]。
召されたものは伝道に対する情熱を持つ
聖書の中に出てくる召された人々からわかることは、召命を受けた者は伝道に対する情熱で燃えている状態になるということです。
サウロはダマスコの途上で召命されたとき、「主よ、わたしは何をしたらよいでしょうか」(使徒行伝22章10節)と尋ねました。その選択が好むと好まざるとに関わらず、主に従っていく、そのような情熱を召命された者は持っているのです。
神に召された働き人はここまで献身したらいいというような精神ではなく、神のためにすべてを献げていきたいと考えていくような人でもあるのです。
召されたものは共同体によって承認される
また次の聖句を読むと、召命は共同体によって承認されるものであることもわかります。
一同が主に礼拝をささげ、断食をしていると、聖霊が「さあ、バルナバとサウロとを、わたしのために聖別して、彼らに授けておいた仕事に当たらせなさい」と告げた。
使徒行伝13章2節(口語訳)
召命は具体的な行動を伴うもので、それにより共同体もその召命を承認できるのです。
召されたものはキリストとの個人的な体験を持つ
神に召されていた者が持っていなければならないものとして、キリストとの個人的な経験をあげることができます。
これと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まって来た。
マルコによる福音書3章13節(口語訳)
弟子たちがキリストの12弟子に選ばれ、多くの人々をキリストのもとに引き寄せられたのは、彼らがキリストのもとに来ていたからです。
彼の言葉を教える人々は、その言葉を個人的な経験の中で体験しなければなりません。彼らは、キリストを自分の中に持つことが彼らに知恵や正義、そして、聖別や贖いをもたらすことを体験していなければなりません[8]。
キリストとの個人的な経験つまり、キリストのもとに行かずしてキリストの働き人になることはできないのです。神に召された者はキリストとの個人的な経験を必ず持っているのです。
召しを感じていることは、召しの証拠にはならない
興味深いことに「召しを感じていること」が召しの資格として、1テモテ3章とテトス1章にあげられていないのは、注目に値します。
実際に、多くの人が証言しているように、彼らの召命は、突如として目を見張らせるような出来事として起ったのではなく、徐々に深まる確信であり、彼らの生涯のうちに行われた神の働きが次第に明確化された過程にほかならなかったのである[9]。
つまり、召しとは一時的な感情ではなく、神の働きが明確化されるプロセスであると言えるでしょう。
召命とは、心を照らして、生活に対するご自身の計画を明らかにしてくださる神の人格的な導きと定義してよいであろう[10]。
そう考えたときに、安易にこれが「召命」であると特定の職業や奉仕を絶対化することは避ける必要があるとわかります。
そして、この「召し」とはどのような進路を選ぶのか、どのようなキャリアアップをしていくのかという質問に答えるものではなく、どのように神に献身していくのかという質問に答えるものなのです。
中世・宗教改革時代には「生活の目的は、どうしたら天の御国に行けるか、どうしたら来世のための救いが得られるか、ということであった」[11]。
クリスチャンの労働観と一般的な労働観の違い
一般的な仕事についての考え
内閣府の「国民生活に関する世論調査令和元年度」を見てみると、半数以上が「お金を得るために働く」と答えています[12]。また統計数理研究所の調査によると、じつは必ずしも日本人が特段に仕事一筋というわけではないことがわかります[13]。むしろ、余暇を大切にしたいと思っている傾向が他のアジア圏の地域と比べて強くあるのです!
日本の一般的な仕事についての考えは、この二つの調査をもとに考えると、生活維持のための収入を得るためであり、また余暇を守りたいという傾向があるといえるでしょう。
その一方で、一生楽できるお金があったとしても仕事を続けたいという声も調査の中にはあり、自己実現の目的も見られます。それは社会的意味や個人的意味とも言いかえられますが、内閣府の調査でも、約39%がそれらの意味を労働に見出していることがわかります。
生活維持のための手段であり、また承認欲求と自己実現欲求を満たすためのものであるというのが、一般的な仕事についての考え方といえるのではないでしょうか。
創世記から見る「仕事」
一般的な仕事についての考え方が「生活維持のための手段であり、また承認欲求と自己実現欲求を満たすためのもの」とするならば、聖書の価値観は「仕事は神に仕える行為」です。
創世記2章15節と19節には、天地創造の時点で人が労働に携わっています。
つまり、聖書の中で労働は「社会の一員として務めを果たすため」、もしくは「人を助ける手段」ではないです。
それで人は、すべての家畜と、空の鳥と、野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。
創世記2章20節(口語訳)
つまり、アダムは1人の時点で働いていて、「社会の一員として務めを果たすため」、もしくは「人を助ける手段」として労働が存在していたわけではないのです。
その第一の名はピソンといい、金のあるハビラの全地をめぐるもので、その地の金は良く、またそこはブドラクと、しまめのうとを産した。
創世記2章11ー12節(口語訳)
創世記2章11節と12節には、お金を得る手段としての仕事ではないこともわかります。さらに、創世記2章16節を見ると生活の保障がされていたこともわかります。
主なる神はその人に命じて言われた、「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい」
創世記2章16節(口語訳)
つまり、エデンの園において仕事は、生活維持の手段でも、自己実現の手段でもなかったのです。仕事を評価してくれる他の人や助ける相手、また生活のために働く必要がないときから、アダムには仕事が与えられていました。
創世記2章15節を見るとアダムには、園を管理する役割が与えられていたことがわかります。
ここで「守る」と訳されているヘブライ語の語根“シャーマル”は、しばしば「見守る」、「保護する」を意味[14] (している)。
人が神から与えられた仕事は、神のみ心に従って世界を管理し、育成し、守り、共に祝福を受けるためのものでした。
聖書の仕事についての価値観は、スチュワードシップとも関連しているものがここからわかります。つまり、人は神からその権利と所有物を与えられ、それを管理する役割があるのです。
富を得る力を与えられたのも主であること(申命記8:18)を思い起こさせるものが必要でした。このことのため、主は十分の一献金と諸献金の制度を与えられました。[15]
つまり、お金を稼ぐ手段とその成果は神から与えられたもので、その能力と成果を管理する責任が人間にあるのです。
一般社会の仕事についての考え方の中では、手段と成果に重きを置きますが、聖書の仕事観ではそれ自体をどのように管理するか、ひいてはどのように神に栄光を帰すのかまで考えるのです。
私たちの労働は、今やキリストにおける神の恩寵に対する応答としての感謝の献げものとしての労働であり、愛のわざとしての労働、さらには神の栄光を現わすための労働という意義をもつに至るであろう。これが主イエス・キリストの福音に基づく労働観であると言えるであろう[16]。
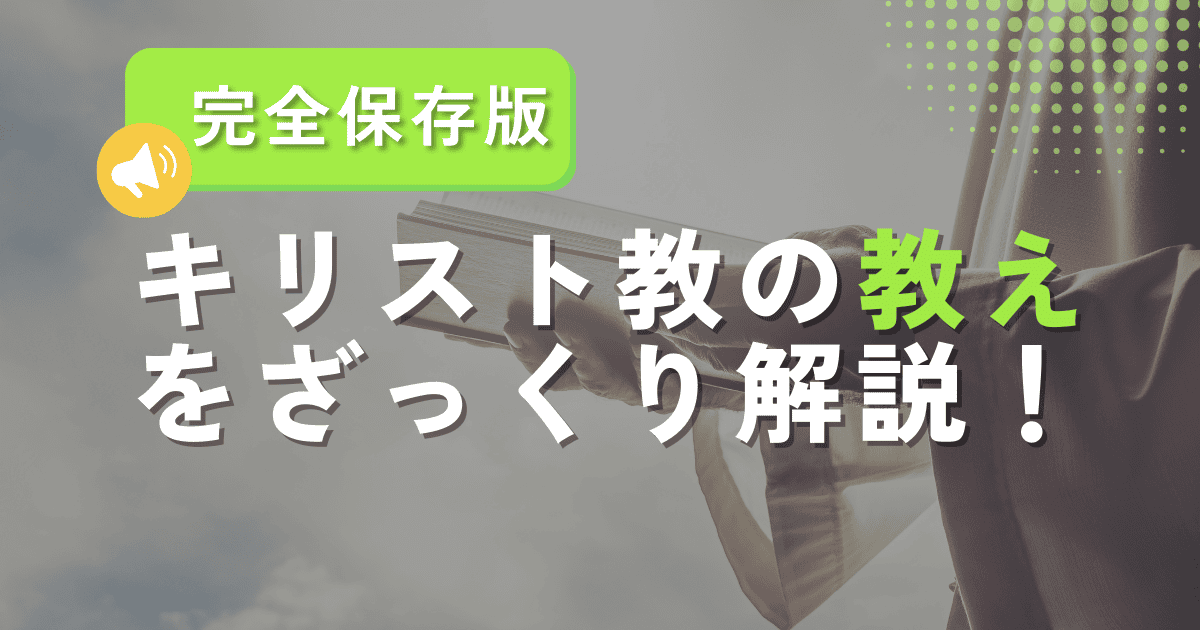
まとめ
お金を得たり、承認欲求や自己実現欲求を満たしたりすることが世間の仕事観ですが、聖書の価値観では、仕事とは「神に仕える」ことです。
そして、ビジネスにおいて成功した者はそれを独占するのではなく、神と人との奉仕のために有益に用いていくことが求められているのではないでしょうか(申命記14:29、26:12、箴言3:9)。
ぜいたくに金銭を浪費することは、貧しい人たちに必要な食物や衣類を与える資力を彼らから奪ってしまう。衣服や家や、家具や装飾の誇りを満足させるために費やされる金銭が、不幸に苦しむ多くの家族のために用いられるならば、それは彼らの苦痛を和らげるであろう。神の家つかさは困窮者に仕えなくてはならない[17]。
また「召し」とは、どのような進路を選ぶのか、どのようなキャリアアップをしていくのかという質問に答えるものではなく、どのように神に献身していくのかという質問に答えるもので、また神の働きが明確化されるプロセスです。そして、それは一時の感情や思いつきによって与えられるものではありません。
そして、この「召し」はただ単に就職や進学を指す言葉ではなく、家庭内において、学校において、職場において、あらゆる場所において、キリストの使者として派遣されることを意味しているのです。
生涯を家庭内ですごすか、普通一般の職業に携わるか、あるいは異教の国へ福音の教師としておもむくかわからないが、皆同じく神の伝道者として、この世に対する恵みの使者となるように召されているのである[18]。
VOPオンラインには豊富なコンテンツがありますが、
さらに学びを深めたい方は
無料の聖書講座『読んでまなぶ』がおすすめです!
\ 詳細はこちらから /
幅広くマンツーマンやグループで学ぶことができる
オンライン聖書講座、
それが『講師とまなぶ』です。
\ 詳細はこちらから /
参考文献
[1]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、38ページ
[2]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、42ページ
[3]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、39ページ
[4]マックス・ウェーバー、中山元(訳)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』日経BP、2010年、121ページ
[5]マックス・ウェーバー、中山元(訳)『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』日経BP、2010年、123ページ
[6]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、69ページ
[7]エレン・ホワイト『教会への証 第一巻 分冊1』福音社、2015年、218ページ
[8]エレン・ホワイト『次世代につなぐ信仰』福音社、2003年、303ー305ページ
[9]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、79ー80ページ
[10]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、73ページ
[11]ジョン・A・バーンバウム、サイモン・M・スティアー、村瀬俊夫(訳)『キリスト者と職業』いのちのことば社、1988年、55ー56ページ
[12]「国民生活に関する世論調査 令和元年度」内閣府、https://survey.gov-online.go.jp/r01/r01-life/2-3.html、(2020年10月20日閲覧)
[13]芝井清久、吉野諒三「職業観・労働観に現れる価値観の多様性と普遍性―「環太平洋価値観国際比較」データの文化多様体解析CULMAN―」データ分析の理論と応用Vol 3、2013年
[14]L.ジェームズ.ギブソン『起源』2013年第一期教課、福音社
[15]SDA世界総会『アドベンチストの信仰』福音社、1995年、467ー468ページ
[16]小田島嘉久『キリスト教倫理入門』ヨルダン社、1988年、238ページ
[17]エレンホワイト『ミニストリーオブヒーリング』13-60神の家宰、298ページ
[18]エレン・ホワイト『ミニストリー・オブ・ヒーリング』福音社、1957年、364ページ