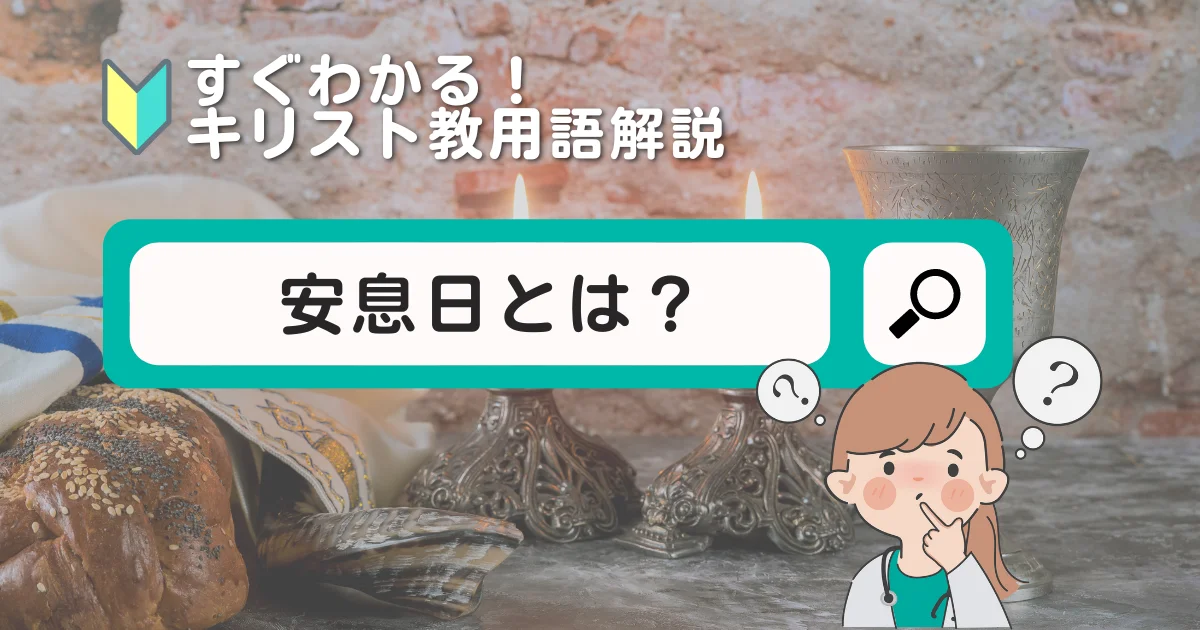
この記事は約10分で読むことができます。

この記事はこんな人におすすめ!
・ユダヤ教の安息日(シャバット)とその過ごし方について学びたい
・聖書が教える安息日がいつなのか、どういうものなのかを知りたい
・なぜ、キリスト教が日曜日を礼拝日にしているのかを知りたい
ユダヤ教の安息日(シャバット)とその過ごし方について、この記事では見ていきます。
安息日は、ユダヤ教の礼拝日として知られていますが、実はキリスト教にも深い関係がある日です!
聖書が教える安息日やキリスト教の礼拝日は何曜日なのでしょうか? その疑問にもお答えします!
安息日とは?
安息日の定義
安息日は次のように定義されています。
(ヘブライ語で)「やめる」あるいは「休み」に由来する。……週の第7日目。休息と礼拝の日として守るように定められた日。
『新聖書辞典』いのちのことば社
ヘブライ語では「シャバット」、英語では「Sabbath(サバス)」と呼ばれる安息日は、ユダヤ教の礼拝日として知られていますが、実はキリスト教にも深い関係がある日です!
安息日は何曜日?その由来は?
安息日は天地創造に由来しています。
天地創造を終えた神は、第7日目を特別に祝福して聖別し、休まれたと聖書には記録されています(創世記1章1節ー2章3節)。
天地万物は完成された。第七の日に、神は御自分の仕事を完成され、第七の日に、神は御自分の仕事を離れ、安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息なさったので、第七の日を神は祝福し、聖別された。
創世記2章1ー3節
「夕べがあり、朝があった。第一の日である」(創世記1章5節)とあるように、聖書の中では、日没から日没までを1日と考えています。
そのため、この第7日目の安息日は、金曜日の日没から土曜日の日没となっています。


なぜ安息日は重要なの?その意味と目的について
創造と救いの記念日
参考箇所はこちらをタップ
出エジプト記20章8ー11節
安息日を心に留め、これを聖別せよ。六日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。六日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを造り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。
申命記5章12ー15節
安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神、主が命じられたとおりに。六日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、牛、ろばなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのために、あなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。
安息日は、モーセの十戒の第4条でも定められていて、そこでは創造と救いの記念日とされています。
モーセの十戒は、出エジプト記20章と申命記5章に記録されていて、安息日が定められた理由の強調点がそれぞれ異なります。
出エジプト記20章では創造の記念日として、申命記5章では救いの記念日とされています。
古代イスラエル人は、エジプトで奴隷の身分とされ、しいたげられていましたが、神によってつかわされたモーセに導き出されました(出エジプト)。
そのことを申命記5章では、安息日を聖別する理由としてあげています。
創造の記念日
安息日を心に留め、これを聖別せよ。……六日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを造り、七日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。
救いの記念日
安息日を守ってこれを聖別せよ。……あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのために、あなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。
ユダヤ教の安息日の過ごし方は?してはいけないことは何?
ユダヤ教の安息日は何をする日?
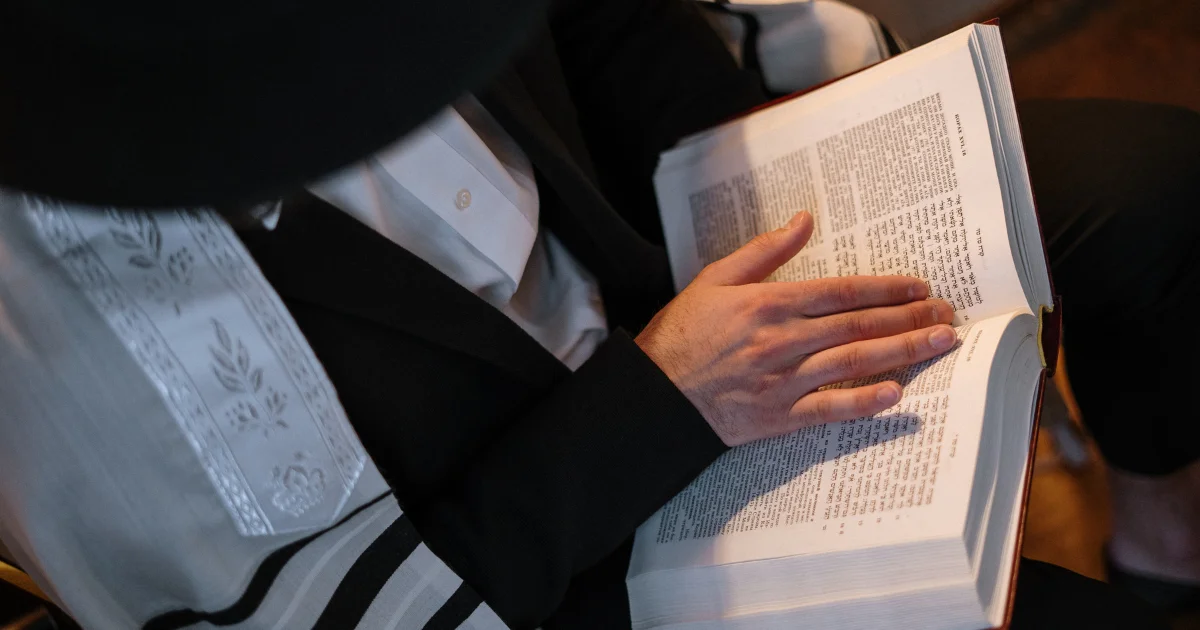
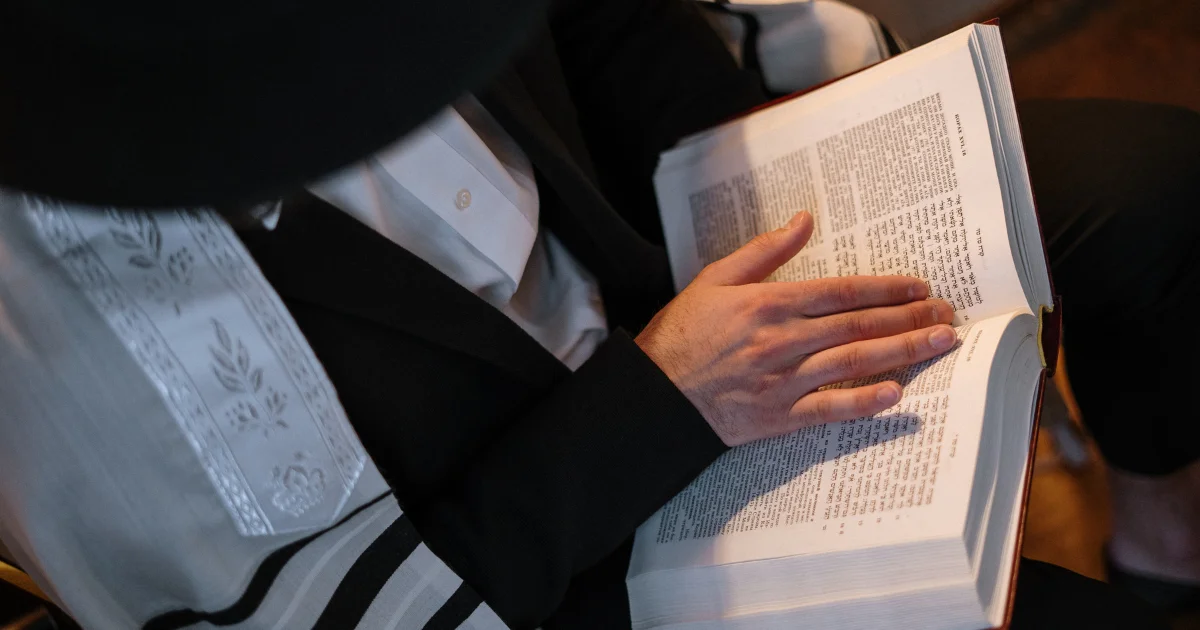
安息日の中心は「礼拝」です。
そのため、シナゴーグへ行き、礼拝に参加することが一番大切なことになります。しかし、それ以外の時間をどのようにユダヤ人たちは過ごしているのでしょうか?
北米最大のユダヤ教系メディアの70 Face Mediaが運営するMy Jewish Learningでは、安息日の過ごし方の例として以下のようなことを推奨しています1。
- 家族や友人と金曜日の夕方に集まって、豪華な食事をゆったりと楽しむ
- ゆっくり昼寝をする
- 散歩に出かける
- 読書や聖書を学ぶ
- 病院や老人ホームを訪問する
メシアニックジューの団体であるUMJCの初代会長を務めたダニエル・ジャスターは次のように述べています。
第一に、安息日は仕事から自由でなければならない。……第二に、この日には、特別な金曜の夜の食事、ロウソクを灯すことや祈りによって、ほかの日と分ける霊的な価値があることである。……
安息日は、また集まって讃美し、御言葉を解説する日としても適している。この日はまた、友人との交流や、家族にとっての日でもある。……一緒に聖書物語を読んだり、静かにゲームをしたり、仮眠を取ったり、友人たちと交流することは、すべて織り交ぜて安息日の喜びとなる。
*メシアニックジューとは、ユダヤ教徒としてのアイデンティティを持ちながら、イエス・キリストをメシア(救い主)であると信じるグループです。
ユダヤ教の安息日に禁止されている行為


「七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない」(出エジプト記20章10節)とモーセの十戒では定められています。
この「仕事(ヘブライ語ではメラハー)」について、ユダヤ教では39に細かく分類して解説しています。
それらは「仕事」というよりも、「作業」という表現の方が適切かもしれません。
たとえば、米国最大のユダヤ教正統派グループの一つであるオーソドックス・ユニオン(OU)では、「お金を扱うこと」、「火を扱うこと」、「書くこと」、「料理をすること」をしないように指導しています2。
この「火を扱うこと」はストーブをつけたりすることだけでなく、車の運転や電気を使うことも含んでいます。
これはガソリンを燃やして車が走るためであるのと、電気は古代の火をつける行為に相当するという理解からです。
また、スマホも電気で動きますし、タイピングも「書くこと」にあたるので、使用できません。
そのため、現代の厳格な正統派のユダヤ人たちの多くは、安息日のための便利グッズを開発してきました。
たとえば、照明が消えるタイマーや料理を温め続ける家電、ボタンに触れなくても自動で開閉するエレベーターなどです。
キリスト教の安息日(礼拝日)は何曜日?
聖書は安息日を何曜日としているの?


モーセの十戒を守って、ユダヤ教徒が土曜日を安息日としていることを見ていきましたが、新約聖書以降、これは変わったのでしょうか?
イエス・キリストは次のように言われています。
「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきり言っておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。
マタイによる福音書5章17―18節
キリストは律法を廃止しておらず、また彼自身、「安息日にいつものように会堂に」行かれていました(ルカによる福音書4章16節・口語訳)。
またキリストの死後、活躍したパウロを含め、使徒たちも安息日の集会に参加し、守っていました(使徒言行録13章42ー44節)。
彼らは、安息日を聖日として守り(使徒言行録17章2節、18章4節)、礼拝するための会堂がない時には、外国人のクリスチャンたちと共に川のほとりに集まりました(使徒言行録16章13節)。
キリスト教の安息日は何をする日?
キリスト教において、ユダヤ教と同じように第7日の土曜日を安息日として守っている教派は少なく、代表的な教派はセブンスデー・アドベンチスト教会になります。
また多くのキリスト教会では、日曜日を礼拝日(主日礼拝)と定め、一部の教派では安息日のように扱っています。
いずれにしても、それらの中心にあるのは「礼拝」になります3。
そのため、午前中は教会の礼拝に参加し、午後は自宅で過ごすか教会のプログラムに参加するのが一般的です。
また、セブンスデー・アドベンチスト教会では、安息日の過ごし方として以下のようなことを推奨しています4。
- 自分自身や家族、従業員が仕事を休めるように計画する(勉強も含む)
- 買い物などを避ける
- 聖書の学びをする
- 散歩、ハイキング、サイクリング、キャンプなど、自然の中に出かける
- 病人や体調の悪い教会員、近所の人たちのお見舞いに行く
- ボランティア活動に参加する
- 聖書を題材にしたゲームや工作で遊ぶ
- 聖書に関連したコンテンツを視聴する
キリスト教の礼拝日が日曜日なのは、なぜ?


礼拝日が土曜日から日曜日に変更された理由は?
一般的に、キリスト教の礼拝日は日曜日であり、主の復活を記念するためであると理解されています。
しかし、当初は日曜日ではなく、今のユダヤ教と同じく土曜日でした。歴史の流れの中で土曜日から日曜日へと変更されたのです。
聖書が示す安息日が土曜日であり、また歴史的に土曜日から日曜日に変更されたことは、セブンスデー・アドベンチストだけでなく、さまざまな多くのキリスト教派で認められています5。
変更された当時、日曜日は、太陽崇拝の広まりと神と太陽(光)を関連付ける伝統から天地創造の第1日目の記念として、また日曜日が「8日目」と表現されたことから永遠の新世界を象徴として考えられました。
現在、一般的に知られている主の復活の記念という意味合いは、当初は強調されず、後に重要な理由となったと、サムエル・バキオキは述べています6。
また彼は、日曜日への変更は聖書的な根拠ではなく、当時の社会的背景から生まれた習慣であるとしています。
ローマ帝国が採用したユダヤ人に対する抑圧的な措置(特に首都では顕著であった)によって、ローマ教会において多数派であった異邦人信徒は、ローマ当局に対してユダヤ教との違いを明確に示すことを促されたようです。そのため、ほとんどのキリスト教徒が依然として守っていた過越の祭りのようなユダヤ教の特徴的な祭りの日付や守り方を、安息日も含めて変えることになりました。
321年に、ローマ皇帝のコンスタンティヌスは日曜日を礼拝日として重んじるようにとの最初の法令を出し7、その後、教会は日曜日への変更を発表しました8。
またカトリック教会は、安息日を日曜日に変更したことを公に認めています。
ピーター・ガイヤーマン(1870―1929)の『改宗者のためのカトリック教義のカテキズム』の中では、次のように書かれています。
Q.安息日はいつですか?
A.土曜日が安息日です。
Q.なぜ土曜日の代わりに日曜日を守るのですか?
A.土曜日の代わりに日曜日を守るのは、カトリック教会がラオディキア公会議(A.D.336)で土曜日から日曜日に厳粛さを移したからです。
カトリックは、礼拝日が日曜日に変更されたことをカトリックの権威によって行なったとしているのです。
またジェームズ・ギボンズ枢機卿(1834ー1921)はカトリックに関心のあるプロテスタントに向けて書いた著書で、次のように述べました。
聖書を創世記からヨハネの黙示録まで読んでも、日曜を神聖化することを認めている箇所は一行もありません。聖書は、わたしたちが神聖化することのない土曜日の宗教的遵守を強制しています。カトリック教会は、わたしたちの主や使徒たちが、霊感を受けた著者が記録していない宗教上のある重要な義務を教育したと正しく教えています。……したがって、わたしたちは、聖書だけでは信仰の十分な指針や信仰の規準にはなり得ないと結論づけなければなりません。
まとめ
天地創造の時、神が7日目に休まれたことに由来した安息日は、週の第7日目(金曜日の日没から土曜日の日没まで)に守られる休息と礼拝の日です。
キリストや使徒たちは安息日を守っていましたが、現在は多くのキリスト教会が日曜日を礼拝日としています。ただ、この日曜日への変更は聖書に基づくものではなく、さまざまな要因が絡み、時代の中で変わっていったものでした。
今もなお、安息日は、十戒にもあるように創造と救いの記念日なのです!


著者|高橋 徹
1996年、横浜生まれ。三育学院カレッジ神学科卒業後、セブンスデー・アドベンチスト教団メディアセンターに勤務、現在はセブンスデー・アドベンチスト教団牧師。
- セブンスデー・アドベンチスト教団牧師
- 光風台三育小学校チャプレン・聖書科講師、三育学院中等教育学校聖書科講師
- 著書『天界のリベリオン』
VOPオンラインには豊富なコンテンツがありますが、
さらに学びを深めたい方は
無料の”聖書講座“がおすすめです!
\ 詳細はこちらから /
参考文献
1 My Jewish Learning. “Ask the Expert: What To Do On Shabbat.” My Jewish Learning, https://www.myjewishlearning.com/article/ask-the-expert-what-to-do-on-shabbat/, 閲覧日: 2024年9月18日
2 Kaplan, Aryeh. Sabbath: Day of Eternity. National Conference of Synagogue Youth/Union of Orthodox Jewish Congregations of America, 1982. 参考にしている「安息日に禁止されている39の作業」については、Orthodox Unionのウェブサイトを参照した(Orthodox Union, “The Thirty-Nine Categories of Sabbath Work Prohibited By Law,” Orthodox Union, https://www.ou.org/holidays/the_thirty_nine_categories_of_sabbath_work_prohibited_by_law/, 閲覧日: 2024年9月18日)
3 「安息日は神礼拝の中心です」『アドベンチストの信仰』430ページ
4 Adventist.org. “How We Can Celebrate the Sabbath Today.” Adventist.org, https://www.adventist.org/the-sabbath/how-we-can-celebrate-the-sabbath-today/, 閲覧日: 2024年9月18日
5 聖書入門.com,「Q.139 日曜日に働くことは罪でしょうか。」https://seishonyumon.com/movie/5007/, 閲覧日: 2024年9月19日
牧師の書斎,「2.『第七日』の神の安息」http://meigata-bokushin.secret.jp/index.php?「第七日目」の神の安息, 閲覧日: 2024年9月19日
Croossroads Internationnal Church,「クリスチャンは、毎週日曜に教会に行かなければならないのか」,閲覧日: 2024年9月19日
6 Bacchiocchi, S. (1977), From Sabbath to Sunday: An Historical Investigation of the Rise of Sunday Observance in Early Christianity, Pontifical Gregorian University Press , 189ー190page.
7 「尊い太陽の日には、都に住む奉公人や民衆を休ませ、すべての仕事場を閉鎖すること」Codex Justinianus, book 3, title 12,law 3; trans.in Philip Schaff’s History of the Christian Church,vol.3,5th edition, p.380.
8 「クリスチャンはユダヤ化すべきでなく、土曜日には休まずに働くべきです。しかしクリスチャンは主の日(日曜日)に神をあがめ、可能な限りその日には仕事を休むべきです。しかし、もしクリスチャンがユダヤ化しているのであれば、彼らはクリスチャンとは見なされません」Charles Joseph Hefele, A History of the Christian Councils,vol.2,p.316.